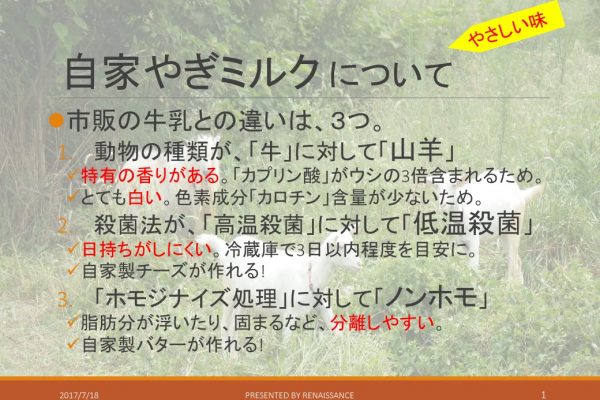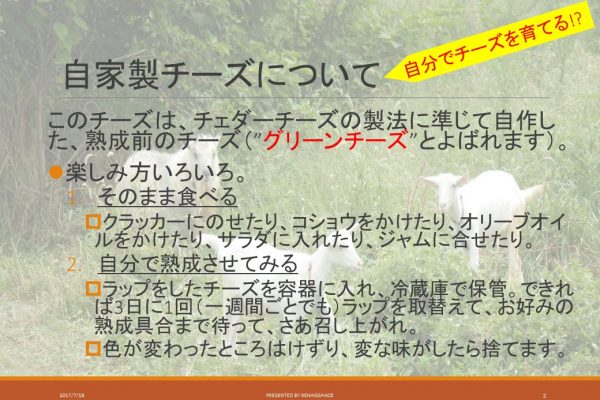"市販の牛乳"と、"自家やぎミルク"のちがいを、もう少し詳しく。
ちがいのポイントは、「成分」と「製法」。
ちがいのポイントは、「成分」と「製法」。
成分について
ミルクは、カルシウムをはじめタンパク質、脂肪、炭水化物、ビタミン類など、私たちの体に必要な栄養素をバランスよく含む、栄養学的にすぐれた食品です。
牛のミルクとやぎのミルクは、主に、「タンパク質」「ビタミン」「脂肪」に違いがあります。
- タンパク質
- いずれも乳タンパク質のカゼインを含んでいますが、牛乳に含まれているαs1-カゼインを、ヤギミルクは含んでいません。αs1-カゼインは、牛乳アレルギー発症の際の主要なアレルゲンとして知られている成分です。このため、ヤギミルクがアレルギーを起こしにくいと言われています。
- なお、ミルクは、カルシウムを体に吸収しやすい形で含んでいます。カゼインの内側にリン酸カルシウムを大量に包み込んだカゼインミセルという形でカルシウムを含むため、本来水に溶けにくいリン酸カルシウムを、大量かつ安定に取ることができます。
- ビタミン
- いずれもビタミンAを豊富に含んでいますが、牛乳に含まれる色素であるカロチンを、ヤギミルクは含んでいません。そのため、ヤギミルクそのもの、そこからできるバターやチーズ、せっけんも真っ白です。
- 脂肪
- 乳脂肪は、ミルクの中で小さな脂肪球という塊で分散しています。ミルクの中では、乳脂肪は直径 0.1 - 10 µm の塊となって分散しています。
- ヤギミルクは、脂肪球の粒度分布が牛乳より小さい方に偏っており、平均粒径が3.49μmで、牛乳の4.55μmより小さくなっています。なので、搾りたての状態では、ヤギミルクはよりまろやかな味に感じるといわれています。
製法について
- 殺菌方法
- 私たちのヤギミルクは、「低温度殺菌」、63℃~68℃で30分かけて殺菌する方法を用いています。ゆっくり殺菌するので、タンパク質の変性が少なく、生乳にちかい、すっきりとしたのどごしとほのかな甘みを感じることができます。市販の牛乳は、「超高温度殺菌」、120℃~130℃で2秒加熱して殺菌する、大量生産に向いた方法を用いています。栄養成分は同じですが、タンパク質の構造は変わるため、風味やのどごしが変わってきます。
【参考】タカナシ乳業(株)http://www.takanashi-milk.co.jp/products/ltlt/01.html - 高温殺菌されたミルクは、チーズ作りに適していません。高温で加熱するとホエイ中のβラクトグロブリンがカゼインミセルと結合してレンネットとの反応が起こり難くなり、カードができにくくなるためと言われていますが、詳細な原因はよくわかっていないようです。
- 私たちのヤギミルクは、「低温度殺菌」、63℃~68℃で30分かけて殺菌する方法を用いています。ゆっくり殺菌するので、タンパク質の変性が少なく、生乳にちかい、すっきりとしたのどごしとほのかな甘みを感じることができます。市販の牛乳は、「超高温度殺菌」、120℃~130℃で2秒加熱して殺菌する、大量生産に向いた方法を用いています。栄養成分は同じですが、タンパク質の構造は変わるため、風味やのどごしが変わってきます。
- ホモジナイズ処理
- 私たちのヤギミルクは、「ホモジナイズ(均質化)」処理をしていません。
そのため、まろやかで、濃厚なミルクの味を楽しめる一方、保存中のミルクの表面に塊=乳脂肪が浮かびやすくなっています。市販の牛乳は、「均質化」処理により、脂肪球の大きさを均一にそろえています。 - 均質化処理により、ミルクの保存安定性が高まります。具体的には、(1)保存中に乳脂肪が液面に浮かんでこない(脂肪球がクリームとなって分離することがない)、(2)乳脂肪の消化吸収が良くなる、溶解する酸素の量が減り、保存性がよくなります。均質化処理の方法は、牛乳に高圧をかけて、狭くて曲がっている管の中を高速で通過させ、大きな脂肪球を砕き、、直径 0.1 - 10 µmとばらつきのあった脂肪球を平均して直径 3 µm 程度にするという工程で行われます。均質化処理をしたミルクは、まろやかさが減り、味が薄くなると言われています。
- 私たちのヤギミルクは、遠心分離させると濃度差で"生クリーム"を採ることができ、さらに水を分離させて"バター"を作ることができます。均質化処理がされている市販の牛乳からはバターを作ることができません。市販の生クリームからバターを作ることはできます。
- 私たちのヤギミルクは、「ホモジナイズ(均質化)」処理をしていません。
参考資料